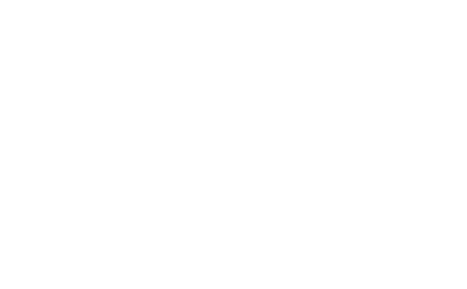第5章 葛藤と決断(母)
そこに気がついた私は、今度は、とてつもなく大きな葛藤に苛まれた。
理想を追い求めるなら、なぜ、自分でやらないのだ。人を責めるだけの資格は果たしてあるのだろうか。良いものであると信じているならば、全てを投げ打ってでも、その普及に全身全霊を投げ打って進めば良いではないか?という事である。
しかし、それは、安定した大企業の生活を捨て去ることを意味していた。私には、家の35年ローンが残っており、私立の高校と中学に通う愛しい子供達がいた。家族を路頭に迷わせるわけにはいかない。そして、事業の成功は極めておぼつかない。 なにせ、今まで誰も見向きもしてくれなかった商品なのである。
しかも、私はそれを推進しようにも、それができるだけのものを、本当に何一つ持っていなかった。一般市場に売った経験もなく、製造知識もなく、資金もなく、販売ルートもなく、自分では回路図すら読めない。
こうも思った。もしかしたら、“この技術は間違いなく社会のためになる”等という信念は、自分の勝手な思い込みなのかもしれないと。もし、本当に必要な存在なら、なぜ、今まで誰一人、本気になって動いてくれる仲間が見つからなかったのだ、と。
「やめてしまえ。今までよくやったよ」
こう囁く自分がいた。今、これを放棄しても誰も私を非難する事はない。誰に迷惑をかけることもない。人生において、こんなことをここまで挑戦した、という自分なりの勲章もできたではないか。酒飲み話でも結構面白いネタになるはずだ。こう言う自分がそこにはいた。
しかし、私は、どうしてもそれを捨てることは、またもやできなかった。頭ではその危険性は十分すぎるほどわかっていた。
つまるところ、この選択は、
『私は、一人の人間として、いかに生きるべきか』
という壮大な問いかけでもあったからである。
『安定か、挑戦か』、『社会への貢献か、自己満足か』、『妥協か、理想か』これらの一つ一つの答えを見つけるためには、“自分がいかに生くべきか”の答えなしにはできないものだった。
私は、会社の営業としては、かなりの営業実績を上げたスーパーセールスであった。営業でありながら、商品を作りながら販売を生み出していくスタイルでは、自分の横に出るものはいないと思っていたし、ある意味、事実でもあった。
しかし、昇進昇格には全く恵まれなかった。そして、会社が縮小しだすと、内向きのスマートなスタイルが主流となり、外で活躍するセールスマンの居場所がどんどん小さくなっていくような気がした。まるで、太平の世の中になった、時代遅れの武辺者の古武士のようでもあった。
そんな風潮の中で、生き残るためには、給料のためと割り切って9時から5時まで座り、可もなく不可もなく、仲間内で上司も含む人間関係を重視する生き方が賢い選択だとは知っていた。
しかし、同時に、自分の人生はこんなもので良いのだろうか。こんなことで定年までの残りの10数年過ごしても良いのだろうかという思いが常に自分の頭にあった。ここで何もかも諦めて、周囲に同調して生きていく事が本当に良い事だろうか?将来、もし、この夢のLED電球の話を思い出した時に、自分は一体どんな気持ちでいるだろうか? そこで湧き上がる感情は、間違いなく後悔の念ではないのか?
そこまで考えても、私は、どうしても決められなかった。しかし、そんな決断力のない私に、思いもよらなかった大きな衝撃が舞い込んできたのである。
それは、一本の電話による知らせであった。一瞬にして、私を不幸のどん底に落とす人生最大の不幸の知らせであった。母が治療方法のない難病で、治療方法がなく待っているのは『死』でしかないという知らせである。筋萎縮性側索硬化症(ALS)という病気であった。
母は、幼い頃に両親を亡くし、親戚に引き取られながら2人の妹を養育し、父と結婚してからは、厳しく、優しく、愛情たっぷりに私たち兄弟を育ててくれた。明るい性格で誰からも好かれていた。昔の日本人の凛とした気高さと、現代風の明るさを持った人だった。
私はその事実に狼狽し、悩み、今までの親不孝を後悔した。後悔どころか懺悔であった。フォークダンスが好きで、元気に飛び回っていた母は、日本の平均寿命からすると、あと20年は生きていると思っていた。
まだ、先がある、いずれ親孝行しよう、今は、自分の子供を育てるのに手一杯だし…そう考えて、親孝行などほとんどしなかった。本当に。その知らせを受けた時に、自分が限りなく情けなかった。
そして、この事実は、私は、重大な決心をさせたのである。
「今を生きよう。今を大事にしよう。明日があり続けると思ってはいけない。そして母は、事なかれ主義で生きる道を選択するために、私を一生懸命に育ててくれたのだろうか?厳格で優しい母は、最後は、何をしても、あの世で再会したら、よくやったと、褒めてくれるだろう。でも、自分が納得できない人生を送ることは、母はきっと望まないだろう」
ついに、私は、『今を必死に生きる』事を決断した。
病気の母に余計な心配をかけたくないため、この決意は最後まで母には伝えなかった。そして、母は、病気が発覚してからわずか1年ほどで静かに息を引き取った。
私は、病気によって口も、手足もほとんど動かなくなってしまった母の、結果的には最後の別れになった際の『頑張りなさいよ』という、優しくも、力のこもった母の眼差しは、今でもはっきりと覚えている。それは、私にとって、今でも第二の人生の、“道しるべ“になっている。